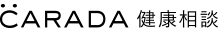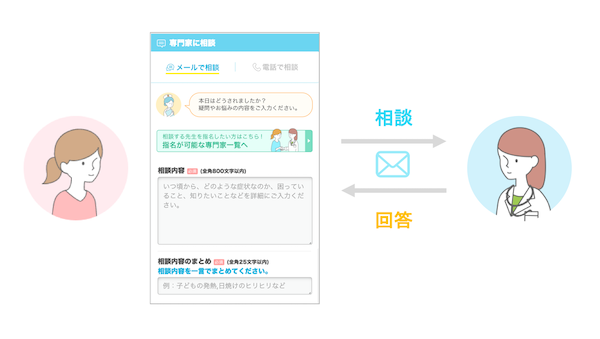相談者:ランボーさん(53歳/男性)
本年8月19日に92歳になる母が誤嚥性肺炎で入院し、入院後にMRSAへの感染が判明しました。
治療の結果、9月末に経鼻経管栄養を開始するまでに回復。
しかし、カテーテルを通した直後から肺炎を再発し、喀痰の増加、発熱が見られ、今は経鼻経管栄養は中止されております。
今後は点滴栄養のみで様子を見るしかないと主治医から言われました。
母は糖尿病を患っており、血小板の数も少なくその機能も衰えている事から、胃瘻の造設は難しく、中心静脈栄養もMRSAによりできない状況です。
一般的に点滴栄養のみでどの位存命が可能なのでしょうか?
個人差があるのは重々承知しておりますが、一般的に医師が判断する範囲で回答願います。